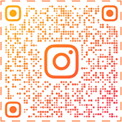所得税法9条1項18号に非課税所得として、損害賠償金で、心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるものと規定されています。本節では、損害賠償(民法)について解説します。1 損害賠償とは?(1) 損害賠償とは?損害賠償とは、他人に与えた損害を金銭で補償することです。民法上の損害賠償の根拠を大別すると、債務不履行による損害賠償(民415条)と不法行為による損害賠償(民709条)の2つがあります。前者は、債権者が契約などによる債務の内容に従った履行をしない債務者に対して行う損害賠償です。一方、後者は、被害者(債権者)が権利を侵害した加害者(債務者)に対して行う一般的な損害賠償です。債務不履行と不法行為の相違点として、下記のとおりです。まず、証明責任です。債務不履行では、債権者が債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであること(債務者の免責事由によるものはないこと)を証明する必要があるのに対し、不法行為構成では、被害者が加害者の故意または過失を立証する必要があります。もっとも、債務不履行構成であっても、債権者が具体的な債務内容を明らかにしなけばならないため、実務上は、証明責任の点では債務者にとって債務不履行のほうが有利であるわけでも必ずしも解消されていないです。2点目は、過失相殺です。過失相殺とは、損害の公平な分担を図るため、被害者の過失を減じる事情を考慮することです。不法行為構成の場合、債務不履行の構成(民418条)とは異なり、損害賠償責任の有無は対象とならず、過失相殺の結果、賠償額がゼロとなることはできません(民722条2項)。また、過失相殺することは義務ではなく、裁判所の裁量によります。もっとも、条文上は上記相違点がありますが、解釈上は同じく解するべきであると考えられています。3点目は、消滅時効期間です。下表のとおり、起算点及び消滅時効期間が異なります(3-2⇒168頁)。ただし、人の生命または身体の侵害の場合は、債務不履行構成であっても不法行為構成であっても主観的起算点から5年間、または客観的起算点から20年間です。不法行為構成の場合に主観的起算点からの消滅時効期間が債務不履行構成よりも短い3年間となっているのは、不法行為は通常、未知の当事者間において偶発的な事故に基づいて発生するものであり、不安定な場に置かれる加害者を保護するためです。◎損害賠償請求権の消滅時効期間債務不履行による損害賠償請求権(民166条1項) 不法行為による損害賠償請求権(民724条) 人の生命または身体の侵害の場合の不法行為による損害賠償請求権(民724条の2)主観的起算点 権利を行使できることを知った時から5年間 被害者らが損害及び加害者を知った時から3年間 被害者らが損害及び加害者を知った時から5年間客観的起算点 権利を行使できる時から10年間 不法行為の時から20年間 左記起算点から20年間Google スプレッドシートにエクスポート(4) 請求の競合債務不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償のいずれを選択できうる場合があります。例えば、使用者が事業のために第三者に損害を加えた場合に、使用者が職場環境に配慮しなかったり、医師が医療過誤により患者に後遺症を負わせた場合です。判例は、請求権の競合を認めており、いずれの損害賠償も選択することができる。2 不法行為(1) 不法行為責任の制限不法行為責任は、物権的請求権や債務不履行責任を補完する役割を果たします。物を奪われた場合、物権的請求権(返還請求権)を根拠として、その物の返還を請求することはできますが、一定期間奪われたことにより生じた損害の賠償請求を行うことはできません。また、契約関係がない相手方から権利の侵害を受けた場合、債務不履行による損害賠償請求をすることはできません。これらの場合であっても、不法行為による損害賠償請求であれば賠償回復を図ることができます。民法709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(2) 不法行為の要件不法行為による損害賠償請求の要件は、①権利侵害(=被害者利益の存在+加害行為)、②加害者の故意または過失、③損害の発生、及び④加害行為と損害との間の因果関係です。(3) 故意または過失不法行為責任においては、過失責任の原則が採用されています。過失のない者は(不可抗力による)結果責任を負わないようにすることにより、個人の行動の自由が保障されています。不法行為の要件となっている故意とは、侵害結果の発生を意欲し、または容認していたことをいいます。また、過失とは、結果を回避するために必要な注意を怠ること(予見可能性)をいいます。注意義務を尽くしても結果を回避できなかったときは過失になりません。注意義務の程度も通常要求されるもので、軽過失であれば不法行為の要件である過失を充たします。それに対し、重過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意をすればたやすく有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」をいいます(判例)。(4) 損害とは?ア 損害とは、不法行為がなければ被害者が置かれていただろう財産状態と、実際の財産状態との差額をいいます。差額を計算するには、財産的損害と非財産的損害に分けて考えます。なお、現実損害を越える賠償を認める懲罰的賠償は、日本では認められていません。財産的損害には、被害者が支払いを余儀なくされる積極的損害(例.治療費、弁護士費用。1-11⇒79頁)と、被害者が利益を得られなくなる消極的損害(例.休業損害、後遺症などによる逸失利益)があります。非財産的損害とは、肉体的・精神的苦痛のことです。苦痛を補填する慰謝料は、生命または身体や人格的な利益の侵害を受けた場合に認められますが、財産権の侵害の場合(例.愛車を壊された場合)には、一般的に認められません。ただし、愛犬などのペット(法律上は物)が殺された場合に慰謝料が認められることもあります。慰謝料は、肉体的・精神的苦痛だけでなく、財産的損害を補填する役割もあるとされています。被害者が将来の低額となった場合に慰謝料を増額することによって全体の賠償額が調整されることもあります。もっとも、慰謝料を認めると賠償額の増額を増加させるおそれがあるため、不法行為(加害者)には、刑事罰及び社会との制裁が与えられることもあります。イ 損害賠償の範囲損害賠償の範囲は、権利侵害と相当因果関係のある損害に限られ、債務不履行の損害賠償の範囲を定める民法416条が類推適用されます。すなわち、通常生ずべき損害によって生じた損害が、損害賠償の範囲になります。(5) 不法行為の効果不法行為に対する救済手段は損害賠償(民709条)、原状回復(回復ではなく)を求めることです(民72条1項が準用する民417条)。3 損害賠償の調整(1) 個人が受け取った場合個人が損害賠償金を受け取った場合、損害を補填するものであり、純資産の増加とならないため、所得税は非課税とされています。例えば、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、休業損害金、医療費などや、資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金は、非課税です。ただし、必要経費を補填する額に相当する金額(例.商品の原料費)及び収入金額に代わる賠償金(例.棚卸資産の損害に対する部分)は、課税されます(所令30条2号)。(2) 個人が支払う場合個人が支払う休業や死亡に関連する損害賠償金は、必要経費に算入できません。また、事業に関連して、製造した商品により個人の権利を侵害した場合に支払う損害賠償金については、所得税の負担を減少させ、支払った損害賠償による負担を軽減するのは相当ではないため、必要経費に算入できません(所税45条1項9号、所基通45条の2)。一方、事業に関連して、軽過失により他人の権利を侵害した場合に支払う損害賠償金は、必要経費に算入することができます。COLUMN 1 貨幣の役割と機能(古代・中世)貨幣の起源は諸説ある。例えば、交換の媒介物としての機能です。物々交換は、常に相手が必要なものとは限らないからです(取引所的な世界)。貨幣の機能として、価値の尺度(社会的な世界)、価値の貯蔵手段としての機能です。貨幣は、交換が容易なため、将来の消費に備えて蓄積されます。古代ギリシャでは、八百屋は一種の物々交換で、負債としての貨幣はあまり存在せず、貴族などが使用していました。ローマ帝国でも、貨幣が普及しましたが、ローマ帝国の滅亡後は、西欧では貨幣が衰退しました。中世ヨーロッパにおいて、11世紀頃から商業が活発化し、貨幣が再び流通し始めました。当初は、金貨や銀貨などの実物貨幣が使用されていましたが、13世紀頃から、銀行券や手形などの信用貨幣が登場しました。16世紀には、重商主義の時代を迎え、国家が貨幣の発行を管理するようになりました。19世紀には、金本位制が確立され、貨幣価値が安定しました。破壊を呪術的機能により再建するためであったと考えることができる。COLUMN 2 税理士の損害賠償責任(1) 債務不履行責任税理士は、依頼者に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことがあります。税理士は、「納税者から信頼される申告の代理行為等を委任されたときは、委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての裁量判断をもって委任事務を処理する義務を負」います。そして、「申告書等の作成・提出に当たり、委任契約に基づく審査義務の一環として、税務の観点から審査する過程で申告がなされ確認するなどの行為を怠り、これが原因として、これに是正した上で申告を行う義務を負」います(東京地判平22[2010]年12月6日判決・判タ1377号123頁)。この義務に違反すれば債務不履行となります。税理士は、過誤を避けるため、契約の締結に際し、契約の対象となる業務の範囲を明確にすること、業務の遂行に当たっては、証拠書類を十分に確認すること、依頼者とのコミュニケーションを密にすることなどが重要です。(2) 付随的義務税理士が、委任事務の明示的な依頼がなかった事項であっても、債務不履行による損害賠償責任を負うことがあります。税理士には、申告の代理において、相続税の納付についてどのような問題があるかを確認し、これがない場合は特に問題はないとして、依頼者に対してどのような援助が可能かを検討し、確認の上で告知・助言を行う義務が、相続税の申告に伴う付随的義務としてあるとした判例(東京高裁平7[1995]年6月19日判決・判タ914号148頁)があります。この義務に違反すれば、債務不履行となります。(3) 法令適合義務税理士は、一般的には税法に関する法令以外の法令について調査すべき義務を負いません。しかしながら、日本国籍を有しないことが調査義務の懈怠が認定されていれば、一般法人であれば相続人が日本国籍を有しない非居住者であるとの扱いを前提に、租税条約の適用があるか否かについて確認すべき義務を負うとした判例(東京地裁平成26[2014]年2月13日判決・判タ1420号335頁)があります。この義務に違反すれば、債務不履行となります。(4) 共同不法行為による損害賠償通達は、国民に対して法的拘束力を持つものではなく(本節のCOLUMN 1⇒192頁)、また、個々の具体的事案に妥当するかの解釈も権威であるため、形式上通達に従い処理することが許されないわけではありません。しかしながら、「税務行政の基本通達に基づいて処理すること、当該具体的事案について基づく通達と異なる解釈適用をすることも、当該通達の見込に反して見解のところ是正処分や申告是正勧告などの結果を招くことも予想されることから」、税理士は、「信頼される税務の専門家として、申告・納税手続に関与するに当たって、依頼者の信頼を裏切らないように、誠実に業務を遂行すべきである」と解されています(大阪高判平13[2001]年10月18日判決・判例時報1854号165頁)。この義務に違反すれば、債務不履行となります。[2] 不法行為責任税理士は、契約関係にない第三者に対して不法行為による損害賠償責任を負うことがあります。税理士が、融資先から求められた会社の決算書の虚偽記載などに関与し、融資先において、金融機関を誤信させて融資を実行させ、これによって損害を被らせたとした判例(仙台高裁昭63[1988]年2月26日判決・判例時報993号181頁)があります。POINT 1民法上の損害賠償の根拠を大別すると、債務不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償の2つがある。両者は、消滅時効期間が異なる。民法715条(使用者等の責任)1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。3項 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。2 使用者責任の要件被害者が使用者に対して使用者責任に基づく損害賠償請求をする場合の要件は、①被用者の行為が不法行為責任(民709条)の要件を充たすこと、②使用者と被用者との間に不法行為時に使用関係があったこと、③被用者の不法行為が使用者の事業の執行について行われたことです。②の使用関係には、個人事業者(自法人)だけでなく、法人(本節のCOLUMN 1)も含まれます。また、②の使用関係は、契約関係の有無は重要ではなく、実質的にみて使用者が被用者を監督すべき関係にあれば足りるとされています。例えば、元請負人と下請負人の被用者との間に使用関係が認められることがあります。なお、使用者が相当の注意をしたときなどは損害賠償責任を免れると規定されていますが(民715条1項但書)、実際に免責されることはほとんどありません。3 使用者から被用者に対する求償権損害賠償の支払いをした使用者は、被用者に対して求償権(償還を求める権利)を行使することができます(同条3項)。もっとも、使用者は、被用者を用いることによって侵害の危険をつくりだし、利益を上げている使用者側は、信頼により求償権の行使が制限されます。使用者が損害全額を負担すべき場合もあり得ます。「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して、求償することができる」(判例)。4 被用者から使用者に対する求償権(逆求償)損害賠償の支払いをした被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができます(最高裁令2[2020]年2月28日判決・裁判所Web)。理由は、①報償責任及び危険責任の考え方は、使用者と被用者との内部関係にも及ぶ、②使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合と、使用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でないからです。なお、被用者が損害全額を負担すべき場合もあり得ます。COLUMN 2 法人の不法行為法人の不法行為に対する損害賠償請求は、信義則上相当と認められる賠償請求による損害賠償請求というような方法ではなく、直接、法人の不法行為として不法行為による損害賠償請求(民709条)をすることもできるのでしょうか。法人に対する不法行為による損害賠償請求は、被害者が具体的な使用者の不法行為を問題とする必要がないというメリットがあります。裁判所の判断は分かれており、法人に対する不法行為による損害賠償請求について、肯定するものと否定するものとがあります。否定する学説は、法人について心理状態を観念できず法人の過失を論ずることができないことなどを理由として挙げています。COLUMN 3 交通事故令和3(2021)年度税理士試験の法人税法の計算問題では、交通事故に関する出題があり、損金処理した賠償金として、「取締役A氏の業務外の交通違反による交通事故賠償金1万円(人身A氏の業務中の交通事故による交通違反金15万円)がある」と記述されています。令和元(2019)年度及び平成27(2015)年度においても出題されています。交通事故は、自動車などの運転中の道路交通法違反行為のうち、飲酒、無免許運転などに悪質で危険なものを除いたものの(「反則行為」)は、一定期間内に反則金を納めると、刑事罰は科せられないという行政上の特別の仕組みです。反則行為は犯罪であり、本来は刑事手続となりますが、大量発生する事件の処理の迅速化を目的として、この制度が設けられています。反則行為は、交通事故割合制度の適用を受けるか、拒否するかを選択することができ、拒否して反則金を納めなかった場合、必ずしも起訴されるわけではなく、不起訴処分になることもあり得ます。交通事故を起こして支払った損害賠償の関係として、所得税法上、必要経費に算入することはできません(45条1項7号)。また、法人税においては、業務遂行に関連してされた行為に係る交通反則金は損害金に算入され、その他に係るものは給与と定められています(法基通9-5-8)。POINT 1使用者が事業の執行について第三者に不法行為により損害を加えた場合、使用者は被用者に対して損害賠償責任を負う。使用者責任の要件は、①被用者の行為が不法行為責任の要件を充たすこと、②使用者と被用者との間に不法行為時に使用関係があったこと、③被用者の不法行為が使用者の事業の執行について行われたことである。損害賠償をした使用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができる。また、損害賠償の支払いをした被用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。